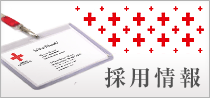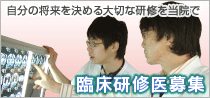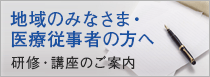| 研修名 | ねらい |
| 救護班要員登録者研修1 | 国内緊急型対応ユニット(dERU)の設営から初動時に救護活動を展開するために必要な基礎的な知識と技術を習得します |
| 救護班要員登録者研修2 | 赤十字救護班要員として災害現場において適切な判断を下すために、dERUの運用を含めた総合的な救護活動をするための知識と技術を習得します |
| 救護班要員登録者研修3 | 赤十字救護班要員としてDMATとの協働を考慮した災害急性期の初動体制について、及びdERUを活用した被災地域救護活動についての総合的な知識と技術を習得します |
| 研修名 | ねらい |
| KYT(危険予知トレーニング)の考え方と実際 | 医療安全に関する知識等を学ぶことにより、職員の医療安全に対する意識の向上を図ります |
| ワークショップ① 事故事例分析から対策を考える |
医療事故を防止し、安全な医療が提供できるよう事故事例の分析を行い業務の見直しを行います |
| ワークショップ② 事故事例分析から対策を考える |
医療事故を防止し、安全な医療が提供できるよう事故事例の分析を行い業務の見直しを行います |
| 医療安全講習① エアウェイスコープの使い方 |
エアウェイスコープによる簡便、確実な気道挿管実習と挿管困難症例に対する外科的気道確保実習、また安全に施行できるエコー下CVC実習を行うことにより医療事故を防ぐことを目指します |
| 医療安全講習② 外科的気道確保実習 |
|
| 医療安全講習③ エコー下CVC実習 |
|
| 安全な薬の投与 -ハイリスク薬について- |
ハイリスク薬の作用、副作用、取り扱い方法などを理解し安全な使用方法を身につけます |
| 抗がん剤曝露の現状と対策 | 抗がん剤の危険性と取り扱い方法を理解し、安全な使用方法を身につけます |
| 医療現場の事故予防1 -針刺し事故とその予防- |
医療現場を改めてしっかりと見直しましょう 針刺し事故の現状とリスク分析から対策について考え、医療現場で働く人々の安全と健康について考えます |
| 医療現場の事故予防2 -伊勢赤十字病院の針刺し事故の実態と対策- |
伊勢赤十字病院でもなかなか減らない針刺し事故。当院の実態と対策についてお話しし、現場に即した事故予防について考えます |
大規模災害救護訓練
| 研修名 | ねらい |
| 災害発生!! 緊急事態を乗り越えよう |
被災者受け入れ病院となった事務職員の果たすべき役割について学びます |
| トリアージの知識・技術を習得しよう -トリアージ実施者研修- |
トリアージの目的・実施方法を理解し、1次トリアージ・2次トリアージの正しい実施の仕方を学びます |
| 地震災害対策 図上訓練 |
地震による大規模災害等を想定し、災害対策本部の開設・運営にかかる図上訓練を実施し、災害対応力を強化するとともに、関連機関との連携のあり方について考えます |
| トリアージの知識・技術を習得しよう -主事研修- |
トリアージの目的・実施方法を理解し、1次トリアージの正しい実施の仕方とトリアージタグの書き方を学びます |
| 被災者搬送のための技術を習得しよう | 被災者を搬送する手段として輸送車・車イスへの安全な移動・搬送方法を学びます |
| 研修名 | ねらい |
| 三施設合同研修 (伊勢赤十字病院・日本赤十字社三重県支部・三重県赤十字血液センター) |
赤十字事業の現状と基本方針を理解し、赤十字事業の推進者としての方向性を考えます |
| 赤十字概論 | 赤十字の歴史、理念、組織、活動、国際人道法等を学び、赤十字職員として必要な知識を習得します |
| 災害救護論Ⅰ | 日本赤十字社の災害救護活動に関する基礎的知識を習得します |
| 災害救護論Ⅱ | 災害救護活動に必要なテント設営や搬送方法等基本技術を習得します |
| こころのケア研修 | 災害救護活動に必要なこころのケアについての基礎的な知識・技術を習得します |
| 日本赤十字社 救急法救急員養成講習会 |
平時はもとより災害時等あらゆる場において生命を守り、苦痛を和らげる行動がとれるようにする目的で、赤十字救急法の知識と技術を習得します |
| 健康生活支援講習会 (日本赤十字社家庭看護コース) |
豊かな高齢期を迎えるために疾病の予防・高齢者の自立を目指した介護の方法を習得します ①高齢者の健康と安全のために ②地域における高齢者支援に役立つ知識と技術 ③自立を目指した介護・移動 ④車椅子移動・食事・排泄 ⑤清潔・衣服 ⑥認知症高齢者への対応 |
| 日本赤十字社救急法 短期講習会 (AEDの使い方) |
誰もがどこでもAED(自動体外式除細動器)に対応できるようにAEDの正しい使用方法を習得します |
| 災害救護論Ⅲ | 最近の災害救護活動の現状と課題から災害救護の役割について考えます |
| 研修名 | ねらい |
| 病院事務職のキャリアプランを考えよう | 病院経営・運営を支える重要なポジションにある事務職員のキャリアについて考える機会にします |
| 論理的思考Ⅱ -コミュニケーション研修- |
お互いを大切にしながらそれでも素直に、コミュニケーションすることをアサーションといいます。アサーションは、私たちが望む自己表現とコミュニケーション、人間関係の鍵といえます。さわやかな対人関係を築くためのスキルを学びます |
| 論理的思考Ⅲ <自分のためのリーダーシップ研修> |
自己の強みをベースにした受講者独自のリーダーシップの発揮方法について学びます |
| 接遇Ⅱ | 人と接するスペシャリストとして日々の対応の見直しと、接遇向上のための具体的な知識・技術を再考しましょう |
| 赤十字の基本原則の実践 | 赤十字の理念・赤十字原則の理解を深め、日々の実践の中にある赤十字の原則や赤十字人としての自分を考えます <研修スケジュール> ①基調講演 「赤十字の基本原則」 ②演習と発表 「日々の実践の中にある赤十字の基本原則を考える」 ③レポート 「赤十字を実践するための私の取り組み」 ④報告会 「赤十字活動の実践報告」 |
| 論理的思考Ⅳ <コーチングスキル研修> |
仕事を指導することを通じて、メンバーの能力や可能性を最大限に引き出すコーチングの進め方を学びます |
| 論理的思考Ⅴ <自分とメンバーの知恵を共に活かすためのファシリテーションスキル研修> |
チームメンバー各自の知恵や思いを共有し、自分とチームの課題解決を促進するために役立つ、ファシリテーションスキルについて学びます |
| 診療報酬の仕組みと改訂のポイント | 診療報酬の仕組みについて学び、平成22年度診療報酬改訂のポイントについて学びます |
| 保険診療について | 現在の保険診療査定の現状を知り、よりよい対策を考える機会にします |
| 研修名 | ねらい | |
|---|---|---|
| 年次別研修 | 論理的思考Ⅰ -組織における仕事の進め方- |
一般的な仕事の進め方を学ぶと共に、論理的でわかりやすいコミュニケーション技術を学びます |
| 論理的思考Ⅱ -コミュニケーション研修- |
お互いを大切にしながらそれでも素直に、コミュニケーションすることをアサーションといいます。アサーションは、私たちが望む自己表現とコミュニケーション、人間関係の鍵といえます。さわやかな対人関係を築くためのスキルを学びます | |
| 看護過程事例発表会 | 事例をまとめ、看護を考える機会 発表を共有することで①看護診断②看護過程について学び合う機会にします |
|
| 論理的思考Ⅲ -自分のためのリーダーシップ研修- |
自己の個性や強みをベースにした受講者独自のリーダーシップの発揮方法について考えます | |
| 接遇Ⅱ | 人と接するスペシャリストとして日々の対応の見直しと、接遇向上のための具体的な知識・技術を再考しましょう | |
| 論理的思考Ⅳ -コーチング研修- |
仕事を指導することを通じて、メンバーの能力や可能性を最大限に引き出すコーチングの進め方を学びます | |
| 論理的思考Ⅴ -ファシリテーション研修- |
他部署やチームメンバー各自の知恵や想いを共有し、自分とチームの課題解決を促進するために役立つファシリテーションスキルについての理解を深めます |
レベルⅠ
| 研修名 | ねらい | |
| レベルⅠ | 急変時の看護Ⅰ | 患者急変時の初期対応を学びます |
| 看護技術研修1 | 日常でよく使う看護技術の基礎を習得します | |
| 看護過程と看護診断の基礎知識 | 看護過程・看護診断の考え方を学び、看護のプロセス上の診断の位置づけと診断の導き方について学びます | |
| 看護診断概念 | 看護診断ラベルの背景にある概念を理解し、確実な看護診断を導くための知識を得ましょう | |
| フィジカルアセスメントⅠ | 日常ケアに必要なフィジカルアセスメントの視点を学びます | |
| フィジカルアセスメントⅡ | 呼吸・循環についてのフィジカルアセスメント能力を高めるためにより具体的な知識・技術を学びます | |
| 感染対策の基礎知識 | スタンダードプリコーションについての知識と直面する病棟での感染に対する危険について具体的に学びます | |
| 看護研究Ⅰ | 文献検索の方法を学びます | |
| 褥瘡ケア | 褥瘡ケアに関する基礎知識を学びます | |
| 看護倫理Ⅰ | 倫理の概要を学び、赤十字の理念との関連を考えながら倫理的問題を客観的な視点で理解できるよう事例分析を通して学びます | |
| 急変時の看護Ⅱ | 患者急変時の初期対応技術を習得します | |
| 看護技術研修2 医療機器の取り扱い |
人工呼吸器と輸液ポンプ・シリンジポンプの原理と取り扱い方法について学びます | |
| ナラティブ | ナラティブの意義と書き方を学びます | |
| 静脈注射教育 | 静脈注射を安全に実施するための基礎的知識・技術を習得します | |
| 静脈注射テストSTEP2 | 静脈注射を安全に実施するための基礎的知識・技術を習得します | |
| 静脈注射テストSTEP3 | 静脈注射を安全に実施するための基礎的知識・技術を習得します | |
| レベルⅠ 入職時・年次別研修 |
病院組織論 | 伊勢赤十字病院の職員として必要な知識を習得し、職業人として自覚と責任ある行動について考えます |
| 病院組織論 | 患者と医療者との信頼に基づいた関係について考えます | |
| 赤十字概論 | 赤十字について学び赤十字の組織の一員としてスタートしましょう | |
| 医療安全概論 | 医療従事者としての基本的な姿勢と態度、リスクマネジメントを学びます | |
| 医療安全方法論Ⅰ | 医療事故につながりやすい技術について基礎的知識について学びます | |
| 医療安全方法論Ⅱ ①医療ガスの正しい知識と安全な取り扱い |
医療ガスに対する安全な取り扱い、危険性について学びます | |
| 医療安全方法論Ⅱ ②放射線の安全利用 |
放射線を安全に利用するための正しい知識を学びます | |
| 医療安全方法論Ⅱ ③注射薬品の取り扱い |
日常よく使用する注射薬の知識について学びます | |
| 医療安全方法論Ⅱ ④内服薬の取り扱い |
日常よく使用する内服薬の知識について学びます | |
| 医療安全方法論Ⅱ ⑤麻薬・輸血の取り扱い |
麻薬・輸血についての知識と正しい取り扱いについて学びます | |
| 接遇Ⅰ | ひとりひとりが伊勢赤十字病院の代表者であることを自覚し、医療従事者としての対応力・表現力を身につけましょう | |
| 論理的思考Ⅰ | 一般的な仕事の進め方を学ぶと共に、論理的でわかりやすいコミュニケーション技術を学びます | |
| 病院組織論 | 職場のメンタルヘルス こころのセルフケアについて学びます |
|
| レベルⅠ トピックス |
臨床検査データに影響を及ぼす検体の取り扱い | 検査データの的確な値を得るための検体の取扱い方法と注意点、正しい採取方法を学びます |
| 検査データの読み方・考え方 | 検体が検査結果に与える影響など正しい検査結果を出すための注意点と簡単な検査結果の読み方・考え方を学びます | |
| 心電図の読み方 | 12誘導記録の方法、危険な不整脈、モニター心電図の読み方を学びます | |
| レベルⅠ 専門コース |
薬物治療 | 薬剤についてのエラーは、インシデント、アクシデントレポートの高い割合を占めています。日頃よく使用する薬剤についての知識を深めることでエラー防止の一助となることを願っています |
レベルⅡ
| 研修名 | ねらい | ||
| レベルⅡ | 看護研究Ⅱ | 看護の質を改善するために必要な研究的視点を養うための基礎的知識を学びます ①文献のさがし方・読み方 ②文献検討発表会 ③看護研究のすすめ方 |
|
| 看護倫理Ⅱ | 倫理的問題を客観的に分析し問題を解決する基礎的能力を身につけましょう | ||
| 診療報酬と看護 | 看護と診療報酬について学びます | ||
| フィシ゛カルアセスメントⅢ | 皮膚についてのフィジカルアセスメントの視点を学びます | ||
| 看護における研究倫理 -倫理的配慮のすすめ方- |
看護研究における倫理的配慮とは具体的にどのようなことでしょうか?研究倫理を遵守した看護研究のポイントについて学びます | ||
| レベルⅡ 専門コース |
フィシ゛カルアセスメントⅣ | 根拠をもった呼吸管理を学び、臨床でのケアに活用できる知識と技術を学びます | ①わかりやすい呼吸の生理と解剖 |
| ②ここをみよう! 画像・検査の見方 |
|||
| ③これだけは知っておこう! 酸素療法と血液ガス |
|||
| ④実践しよう! フィジカルアセスメント |
|||
| ⑤実践しよう! 呼吸リハビリテーション -排痰手技(実技)について- 注:実技のできる服装 各自聴診器を準備してください |
|||
| ⑥実践しよう! 呼吸ケア ~看護の視点から~ |
|||
レベルⅢ
| 研修名 | ねらい | |
| レベルⅢ | 看護研究Ⅲ | 看護の質の向上を目指し看護研究論文の完成を目指します |
| スタッフ指導Ⅱ | 後輩の成長をサポートするための教育技法を学びます(教育方法・教育評価・看護技術の評価方法) | |
| 家族ケア | 医療がスピード化・複雑化され家族の対処力が落ち脆弱化している中で家族をシステム的にとらえ、患者とともに支援していく方法を学びます | |
| スタッフ指導Ⅰ | 後輩の成長をサポートするための基礎的知識を学びます | |
| レベルⅢ | 看護の役割と専門性 | 看護の役割が拡大している中で、看護の専門性を発揮するために看護職として必要な知識と力を改めて考える機会とします |
| レベルⅢ | チームで行う退院調整 ~各職種の役割とは~ |
急性期からかかわる退院の調整。その人らしくいきいきと生きる療養の支援を考えませんか。病棟看護師の退院調整の役割を具体的にお話ししていただきます |
レベルⅣ
| 研修名 | ねらい | |
| レベルⅣ | 看護の概念化研修 「私の実践論」 |
自分の看護実践をリフレクティブシンキングし自らの看護実践論を構築します。自分が大切にしてきた看護実践を見つめ、更に看護実践力を深め積み重ねます |
| 赤十字の基本原則の実践 | 赤十字の理念・赤十字原則の理解を深め、日々の実践の中にある赤十字の原則や赤十字人としての自分を考えます <研修スケジュール> ①基調講演 「赤十字の基本原則」 ②演習と発表 「日々の実践の中にある赤十字の基本原則を考える」 ③レポート 「赤十字を実践するための私の取り組み」 ④報告会 「赤十字活動の実践報告」 |
|
| 家族ケア | 医療がスピード化・複雑化され家族の対処力が落ち脆弱化している中で家族をシステム的にとらえ、患者とともに支援していく方法を学びます | |
| レベルⅣ 年次別研修 |
論理的思考Ⅴ -ファシリテーション研修- |
他部署やチームメンバー各自の知恵や想いを共有し、自分とチームの課題解決を促進するために役立つファシリテーションスキルについての理解を深めます |
その他
| 1.静脈注射教育 | |
| 静脈注射教育 | 静脈注射を安全に実施するための基礎的知識・技術を習得します |
| 静脈注射テスト STEP2 |
静脈注射を安全に実施するための基礎的知識・技術を習得します |
| 静脈注射テスト STEP3 |
静脈注射を安全に実施するための基礎的知識・技術を習得します |
| 2.ナラティブ発表会 | |
| ナラティブ発表会 | 同僚や先輩看護師のナラティブの語りから看護を考え共に学ぶ機会にします |
| 3.伝達講習会 | |
| 伝達講習会 | 他者の研修会での学びを共有し、新たな知識を得る機会にします |
| 4.活動報告会 | |
| 活動報告会 (固定チーム) |
各部署での1年間の固定チームでの活動の取り組みを紹介し、自部署での今後の活動を考える機会にします |
| 5.看護研究発表会 | |
| 第64回 看護研究発表会 |
看護への取り組みを紹介し、研究について理解を深める機会にします |
| 6.赤十字救護員登録に必要な研修 | |
| 赤十字研修 ①赤十字概論 |
赤十字の歴史、理念、組織、活動、国際人道法等を学び、赤十字職員として必要な知識を習得します |
| 赤十字研修 ②日本赤十字社救急法 救急員養成講習会 |
平時はもとより災害時等あらゆる場において生命を守り、苦痛を和らげる行動がとれるようにする目的で、赤十字救急法の知識と技術を習得します |
| 赤十字研修 ③災害救護論Ⅰ |
日本赤十字社の災害救護活動に関する基礎的知識を習得します |
| 赤十字研修 ④災害救護論Ⅱ/ 演習 |
災害救護活動に必要なテント設営や搬送方法等基本技術を習得します |
| 赤十字研修 ⑤災害救護論Ⅲ |
最近の災害救護活動の現状と課題を考え災害救護の役割について考えます |
| 赤十字研修 ⑥こころのケア研修 |
災害救護活動に必要なこころのケアについての基礎的な知識・技術を習得します |
| 7.その他の研修 | |
| CVポート研修 | CVポートについての基本的知識を学びます |
看護助手研修
| 研修名 | ねらい | テーマ |
| 看護助手研修1 | 看護助手としてのモチベーションとスキルアップの向上をはかります | ・医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解 ・医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解 ・看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術 ・看護助手に期待すること ・守秘義務、個人情報の保護 ・ケアリングの実践 ・看護助手業務で困っていることと やりがいと課題(GW) |
| 看護助手研修2 | 高齢者・認知症患者への関わり方 コミュニケーションと見守り 尊厳 ・講義、ロールプレイ |
|
| 看護助手研修3 | 感染予防 ・感染対策について(講義) 針刺し、ゴミの処理、リネン類等 ・手洗い(演習) |
平成22年度院内認定コース研修計画
| 研修名 | ねらい |
| 院内認定コース 「がん看護」 |
がん看護に関する専門的知識を習得し、職場内でのケアの推進者を育成します |
| 院内認定コース 「皮膚・排泄ケア」 |
皮膚・排泄ケアに関する専門的知識を習得し、職場内でのケアの推進者を育成します |
| 院内認定コース 「手術看護」 |
手術看護に関する専門的知識を習得し、職場内でのケアの推進者を育成します |
1.ナイチンゲールセミナー
| 研修名 | 内容 |
| 小児科 | 小児科当直を始めるに当たって必要な知識 |
| 整形外科 | 捻挫。靱帯損傷の評価と初期対応(シーネ固定の実践) 頸椎捻挫のサーベイランスと患者説明 |
| 外科 | 外傷患者の初期サーベイランス 創傷処置:デブリ・創洗浄、縫合糸・縫合法の選択など |
| 脳神経外科 | ERでの迅速な神経所見の取り方、意識レベルの判断法 頭部外傷、脳血管障害の初期対応 |
| 皮膚科 | ERで遭遇する皮膚科疾患とその初期対応 皮膚科コンサルトの必要性とタイミング |
| 耳鼻科 | ERで遭遇する耳鼻科・頭頸部外科疾患とその初期対応 耳鼻科コンサルトの必要性とタイミング |
| 眼科 | 眼科的主訴を訴える患者に対する問診・診察法 眼科コンサルトの必要性とタイミング |
| 内科・消化器科 | 嘔吐、下痢、腹痛、発熱等の消化器症状の診断と初期対応 対症療法薬の使用方法 |
| 循環器科 | 胸痛、動悸の鑑別診断 心筋梗塞、心不全、ERでみられる不整脈の診断と初期対応 |
| 内科・呼吸器科 | 呼吸困難、SpO2低下に対する初期対応、酸素投与、挿管の適応、バイパップなどの人工呼吸器の設定について |
| 腎臓内科 | 救急外来での酸塩基平衡(ABG分析について) 緊急透析の適応と腎臓内科コンサルトのタイミングについて |
| 泌尿器科 | 救急外来で遭遇する泌尿器科疾患と対処方法 |
| 産婦人科 | 妊婦に対する対症療法薬の選択法 妊娠・婦人科疾患が疑われる患者への経腹エコー所見 |
| 研修名 | 内容 |
| Wet Lab | 心臓の解剖を理解し外科的基本手技を学びます |
| YRC ICLSコース | 突然の心停止に対して最初の10分間の適切なチーム蘇生を習得します |
| 地域医療における伊勢赤十字病院の役割 -バディホスピタルシステムの目指すもの- |
三重県における地域医療の現状と取り組みを知るとともに、伊勢赤十字病院の果たす役割について考えます。神島を始めとしたへき地医療の経験から「へき地は医師を素敵にする」というメッセージに秘められた講師の思いもお聞きします |
| EBM実践 ~臨床のための情報検索~ |
EBMの実践に必要な情報検索方法を学びます |
| T&A(triage&action) 救急初療コース |
救急診療の現場で致死的疾患、または適切な治療が受けられなければ機能予後にかかわる疾患を見極め、適切な初期対応と安定化を図るための知識・方法について習得します |
| IVR最先端 (アンギオ装置を中心に) |
心筋梗塞・不整脈・くも膜下出血・脳梗塞・腹部出血・癌などに対して行われる新しい治療法を理解するために、アンギオ装置を主にした最先端のIVR(インターベンショナル・ラジオロジー)について学びます |
| 感染症診療の基本 | 感染症診療の基本を学び適切な初期対応ができるための知識を習得します |
| コース名 | ねらい | 研修テーマ |
| 糖尿病ケア | 糖尿病治療の実践に役立つ知識を得、日々のケアに活かしましょう | ①糖尿病とは |
| ②薬物療法 インシデントアクシデントから |
||
| ③糖尿病ケア Q&A |
||
| 手術を受ける患者のケア | 手術を受ける患者の術前ケアのエビデンス、術中の情報から術後に必要なケアを学びます | ①手術看護の実際と術前ケアに必要な知識パート1 |
| ②術前ケアに必要な知識パート2 | ||
| ③全身麻酔を受ける患者のケア | ||
| ④脊椎麻酔・硬膜外麻酔を受ける患者のケア | ||
| NST専門 | 入院患者の低栄養を撲滅することを目指し、日々の実践に役立つ知識を得、ケアに活かしましょう | NST専門① 検査と栄養 |
| NST専門② 嚥下訓練 |
||
| NST専門③ 嚥下障害 |
||
| NST専門④ 口腔ケアについて |
||
| NST専門⑤ 摂食障害について |
||
| 生命維持管理装置 | 生命維持管理装置の原理を理解して使用する事により、医療の安全を目指します | ①急性血液浄化法 |
| ②補助循環 | ||
| ③人工心肺 | ||
| ④人工呼吸器 | ||
| がん専門 | がんについての最新の専門的知識を学びます | がん専門① 肺がん 総論(診断・治療) |
| がん専門② 肺がんの病理 |
||
| がん専門③ 肺がんの外科的治療 |
||
| がん専門④ 肺がんの内科的治療 |
||
| がん専門⑤ 肺がんの緩和ケアと看護 |
||
| 放射線治療をうける がん患者のケア <放射線皮膚炎> |
放射線治療の原理や有害事象、セルフケア支援を中心とした看護ケアについての知識を共有します | ①放射線療法の基礎知識 |
| ②放射線治療の実際における照射の実際 | ||
| ③放射線皮膚炎のケア | ||
| がん患者の痛みのケア (基礎編) |
がん患者の抱える苦痛を理解し、疼痛マネジメントの方法を中心に学びます | ①トータルペイン |
| ②がんの痛みの種類 | ||
| ③痛みのアセスメント | ||
| ④オピオイドについて | ||
| ⑤オピオイドの副作用対策 | ||
| ロールプレイでふりかえる 困難な場面のコミュニケーション |
日々のケアで困った場面をロールプレイでふりかえり、求められる対応について考えます | ロールプレイでふりかえる 困難な場面のコミュニケーション① |
| ロールプレイでふりかえる 困難な場面のコミュニケーション② |
||
| 呼吸ケアコース | 根拠をもった呼吸管理を学び、臨床でのケアに活用できる知識と技術を学びます | ①わかりやすい呼吸の生理と解剖 |
| ②ここをみよう! 画像・検査の見方 |
||
| ③これだけは知っておこう! 酸素療法と血液ガス |
||
| ④実践しよう! フィジカルアセスメント |
||
| ⑤実践しよう! 呼吸リハビリテーション -排痰手技(実技)について- 注:実技のできる服装 各自聴診器準備してください |
||
| ⑥実践しよう! 呼吸ケア ~看護の視点から~ |
||
| 感染対策の基礎 | 病院における感染対策の正しい知識と方法について学びます | ①手指衛生 |
| ②標準予防策・経路別予防策 | ||
| ③少し気になる細菌の話 | ||
| 褥瘡ケア・初級コース | 褥瘡のリスク評価、褥瘡対策ケア(体圧分散やスキンケア、栄養管理)、局所治療法について学びます | ①褥瘡リスクアセスメント |
| ②体圧分散ケア | ||
| ③褥瘡のスキンケア | ||
| ④褥瘡の栄養管理と食事 | ||
| ⑤褥瘡評価 DESIGN-R | ||
| ⑥褥瘡の治療(創傷治癒過程含む) | ||
| 褥瘡ケア・中級コース | 実技や症例検討を通して、褥瘡のリスク評価、褥瘡対策ケア、局所治療法の実際について学びます | ①摩擦・ずれ力の排除とポジショニング |
| ②症例検討会 「DESIGN評価と褥瘡ケア」 |
||
| 薬物治療 | 薬剤についてのエラーは、インシデント、アクシデントレポートの高い割合を占めています。日頃よく使用する薬剤についての知識を深めることでエラー防止の一助となることを願っています | ①輸液療法 |
| ②抗がん剤 | ||
| ③循環器用薬 | ||
| ④糖尿病薬 | ||
| 在宅支援実践コース | 当地域の現状を理解し、状況に応じた退院調整ができるための知識を身に付けましょう | ①知って得する退院調整に関する制度 |
| ②退院調整における当地域の現状と課題 | ||
| ③退院調整における看護師の役割 急性期からかかわる退院の調整。 その人らしくいきいきと生きる療養の支援を考えませんか。 病棟看護師の退院調整の役割を具体的にお話ししていただきます |
||
| メディカルアロマセラピー 実践セミナー |
日々のケアの場面で患者・家族に、また自分たち同士でケアに関するすべての人に明日から使えるメディカルアロマセラピーの基礎を紹介します | ①ホリスティックメディスン(CAM)と アロマセラピーの基礎知識1 |
| ②マッサージの基礎1(下肢) | ||
| ③マッサージの基礎2(下肢) | ||
| ④ホリスティックメディスン(CAM)と アロマセラピーの基礎知識2 |
||
| ⑤マッサージの基礎3(上肢) | ||
| ⑥マッサージの基礎4(上肢) |
| 研修名 | ねらい |
| 化学療法マニュアルの理解 -臨床実践力向上のために- |
化学療法マニュアルを中心に、化学療法に関する知識と実践力を身につけましょう |
| 関節リウマチの治療方針と看護 | RA(関節リウマチ)の最新の治療とその看護を学びます |
| 診療報酬の仕組みと改定のポイント | 診療報酬の仕組みについて学び、平成22年度診療報酬改定のポイントについて学びます |
| 臨床検査データに影響を及ぼす 検体の取り扱い |
検査データの的確な値を得るための検体の取扱い方法と注意点 、正しい採取方法を学びます |
| がん患者の緩和ケアのコツ ~面接・診断・治療のポイント~ |
がん診療の臨床で必要な、患者への緩和ケアのポイントを学びます |
| 当院の輸血療法の現状 | 安全で適正な輸血療法のための知識を学びます |
| 保険診療について | 現在の保険診療査定の現状を知り、よりよい対策を考える機会にします |
| 緩和ケア病棟での緩和ケア | 平成23年度に予定される緩和ケア病棟開設に向け、看護職を始めとした各職種に必要な知識を、経験者である講師から学ぶ機会にしたい |
| EBM実践 ~臨床のための情報検索~ |
EBMの実践に必要な情報検索方法を学びます |
| 検査データの読み方・考え方 | 検体が検査結果に与える影響など正しい検査結果をだすための注意点と簡単な検査結果の読み方・考え方を学びます |
| 看護における研究倫理 -倫理的配慮のすすめ方- |
看護研究における倫理的配慮とは具体的にどのようなことでしょうか?研究倫理を遵守した看護研究のポイントについて学びます |
| 入院中の認知症患者のケア | 認知症についての知識を深め、援助のポイントと対応の仕方について学びます |
| 心電図の読み方 | 心電図の基礎的な知識を学びます |
| 看護の役割と専門性 | 看護の役割が拡大している中で、看護の専門性を発揮するために看護職として必要な知識と力を改めて考える機会とします。遷延性意識障害患者への講師の取り組みを知る人も多いことでしょう。講師の看護実践についても伺います |
| 脳死下臓器提供の流れ -臓器提供の現場とあっせん対策本部の動きと連携- |
当院は臓器提供施設の指定を受けています 臓器移植に対する基本となる知識を学びます |
| 使えるプレゼン! PowerPoint |
プレゼンテーションの実践のためのノウハウとPowerPointを効果的に活用する方法を学びます |
| IVR最先端(アンギオ装置を中心に) | 心筋梗塞・不整脈・くも膜下出血・脳梗塞・腹部出血・癌などに対して行われる新しい治療法を理解するために、アンギオ装置を主にした最先端のIVR(インターベンショナル・ラジオロジー)について学びます |
| フィッシュ哲学の実践による職場活性化 | 看護職員自らが、楽しい職場、活性化された職場づくりに参加することで、意欲と働きがいが自然とわき上がる職場づくりを考えましょう |
| 防ごうノロウィルス胃腸炎とインフルエンザ | ノロウィルス・インフルエンザの正しい対処法を理解し、感染を拡大させないよう感染対策を学びます |
| アロマセラピーを活かした 簡単リフレクソロジー |
日々のケアの場面で患者さん・家族に、また、自分たち同士で、ケアに関わるすべての人に明日から使えるメディカルアロマセラピーの基礎を紹介します |
| がん化学療法におけるチーム医療 | がん化学療法におけるチーム医療について学び、それぞれの専門職の共働について考えます |
| 褥瘡対策とポジショニングの基本 | 褥瘡発生の要因とそのメカニズムを理解し、ポジショニングの基本知識を学びます |
Ⅰ.救命救急処置技術講習会
BLS/ACLS/ICLS/JPTEC公式コース受講サポート
Ⅱ.認定コース →ICLS、ISLS、JPTEC、NCPR
フォローアップ研修